働き方改革は進んでいますか?働き方改革を進めていくうえで、業務の改善は必須です。
業務を改善には目的がいくつかあります。業務の効率化や行事の見直しなどは、今の労働時間削減にとても効果的です。
これと併せて、もう少し違った視点からも業務改善を進めていきたいです。
こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!
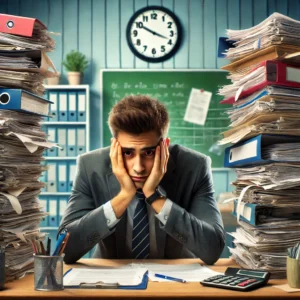
- 経験が無くてもできる業務を増やす
教師は毎日、授業だけでなく、学級経営や部活動、保護者対応など、さまざまな業務を行っています。
その中で、新しく学校に来た先生や若手の先生が「経験がないから上手くできない」と悩む姿を目にすることも多いのではないでしょうか。生徒指導などはやはり経験を積まないと上手くできません。これが先生方の負担を大きくします。
経験がないとできないのであれば、できるようになるまで多くの時間がかかります。もし「経験がないとできない業務」を「経験が無くてもできる業務」に改善できれば、若手の先生も比較的短い期間で戦力になることができます。
例えば、学級通信の作成や行事の準備。ベテランの先生なら、長年の経験から要領よくこなせるかもしれません。しかし、新任の先生がゼロから始める場合、何をどう進めればいいのか分かりません。
保護者対応や学級経営は特に経験に頼る部分が多いです。新任ですぐ担任になった先生にとってみれば、電話一本掛けるのも大仕事です。
転任してきた先生は前任校での経験があります。でも新しい学校ではどうしているのかは分かりません。その結果、準備に必要以上に時間がかかってしまうこともあります。
そこで、過去の学級通信のテンプレートを共有したり、行事の進行マニュアルを整備したりすることで、経験が少ない先生でも負担感が少なく、スムーズに業務を進められるようになります。
また、授業準備についても同じことが言えます。「経験を積めば、よりよい授業ができるようになる」のは事実ですが、そもそも授業の準備に必要な時間を削減できれば、先生方の負担は大きく減ります。
教科ごとに指導案や教材を共有する仕組みを作ることで、一人ひとりがゼロから準備しなくてもよい環境を整えることができます。総合など3年間のカリキュラムと授業内容について学校全体で共有できれば、見通しを持った業務に繋がります。
授業改善のPDCAの回し方を共有できれば、相談もしやすくなります。
何より大事なのは、学校全体で生徒指導の対応や授業改善や評価の方法、生徒指導の方針を決定・共有することです。足並みがそろった対応は生徒や保護者に安心感を与えます。
想定されるトラブルとその解決策をまとめた「対応マニュアル」を作成することで、経験の少ない先生でも適切に対応できるようになります。今本校では、カンニング発生時の超具体的な対応について協議しています。
これらのマニュアルは形骸化しないように定期的に見直しが必要ですが、上手く機能すれば、経験不足や足並みが揃わないことによる対応も減っていきます。
教師は子どもたちの成長を支えるのが仕事です、しかし、経験則ベースで業務が回ってしまうと、教師自身が疲弊してしまいます。
「経験を積めば楽になる」ではなく、「経験がなくてもできる業務に改善する」ことで、本来の仕事である子どもたちと向き合う時間を確保できるようになります。

先生方が少しでも働きやすくなるよう、学校全体で理想の職員室像を共有しながら協力しあい、業務の在り方を見直していければ最高です。

コメント