01 前回
「トップダウン」と「校長先生による決定」、そして「ルートがよく分からない細かい決定」、職員室にはこの3つの意思決定ルートがあります。
これを「うまく機能している」から「変えなくてもいい」と捉えるか、「この中から改善点を見つけだして、もっと仕事をしやすくする。」と捉えるかで、行き先が大きく変わってきます。みなさんはどう思われますか?
どうも、こんにちは。BigWaveといいます。どこの職員室にもいる「教頭先生」。他の先生たちとは違う、奇妙な生態を持つ教師です。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

- 共通目的を土台にした権限移譲を推進する
みなさんの職場にも3つのルートがありますか?私はこれまで5校で勤務しましたが、全ての学校に3つのルートがありました。加えて、20年前からほとんど変わらず運用されています。
これを課題と捉え課題解決を進めると、「教師の自己肯定感向上」「生徒への指導力向上」「効率的で充実した会議の運営」につながります。
結論から言えば、「決定権を分散移譲し、決定から実行までの時間を短縮する」です。そして時短で生まれた時間をより有意義な活動に使えば、いろいろなチャレンジに繋げられます。
とは言え、学校での意思決定権は校長先生にあります。やりたいことがあれば、校長先生からOKをもらう必要があります。そう考えるとかなりハードルは高いようにも感じます。提案する方も大変ですが、何より校長先生が一番大変になります。
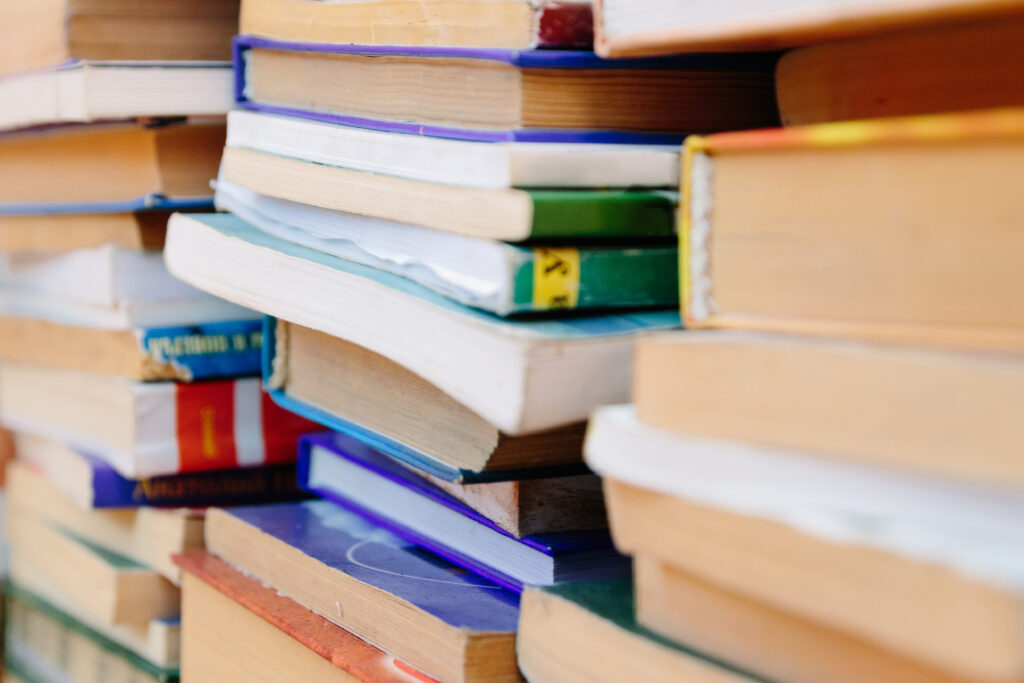
しかし一方で、3つのルートのうちの「ルートがよく分からない決定」においては、毎回校長先生に決定してもらっているわけではありません。
決定権は校長先生にあるのに、実際は決定してもらっていないことが多くあるのが学校現場です。学年の取り組みや生徒委員会活動の内容、部活動運営などです。これはどう解釈すればいいのでしょうか?
これは議論の余地がある部分ですが、個人的には「校訓などの教育目標や校長先生の学校経営方針に沿って立案され、そのまま実行されている。」と考えられると思っています。
そう考えると「ルートがよく分からない決定」は「共通目的に即した個々の決定」と捉えられます。
この意思決定ルートが実際に機能しているのなら、2つ目のルートの「校長先生による決定」で行われている取り組みについても、できるだけ多く「共通目的に即した個々の決定」に移行できるように思います。
例えば「文化祭」についてなら、担当する人たちで最終案まで決定すればいいのです。人数が少ない方が、いろいろと実のある議論ができます。
ただここでやっぱり気になるのは、最終案まで決めたとしても、その後に色々な質問が襲い掛かってくるという心配です。この心配の解消について、次回は見ていきます。

コメント