みなさんの職員室では、新しい企画の決定はどこでされていますか?
教務主任になった年に、ふと疑問に思うことがありました。それまでは、企画の決定を職員会議やそれに先立つ企画会議などで決めていると思い込んでいました。
でもよくよく考えてみると、校長先生に何の相談もせずに実行していた企画が結構ありました。
特に学年での取り組みについては、学年会で決めて即実行といった感じでした。
どうも、こんにちは。BigWaveといいます。どこの職員室にもいる「教頭先生」。他の先生たちとは違う、奇妙な生態を持つ教師です。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!
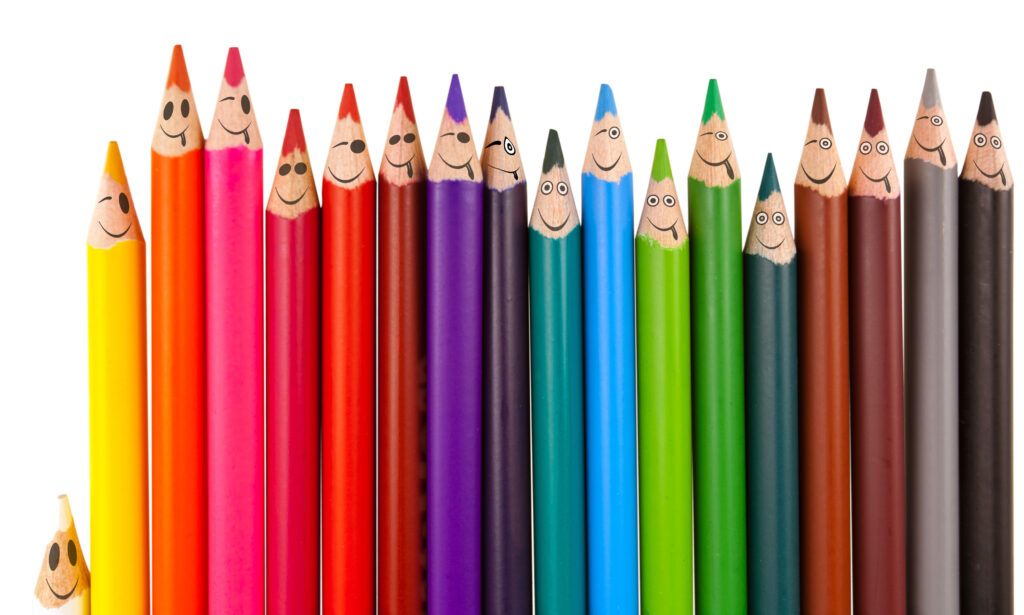
- 実はよく分かっていない意思決定
学校を外から見てみると、トップの校長先生がいて、次いで教頭先生、学年主任そして担任と続いているように見えます。一見するとヒエラルキー構造です。
もしかしたら学校で仕事をしている先生方の中にも、過去の私のように、トップダウンで企画が決まっていると思っている方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに法律上は、教育活動全般を意味する「校務」をつかさどるのは校長先生です。
しかし「校務」には、教育課程に基づく学習指導はもちろん、設備管理、人事関係、PTAや行政機関との渉外まで、ありとあらゆることが含まれます。
ちょっとイメージすれば分かりますが、恐ろしいほど膨大な業務内容です。校長先生がこれら全てに対して、意思決定するのは物理的に不可能です。
例えば「修学旅行に向けての特別活動の内容と流れ」なんかどうでしょうか。校長先生からアドバイスをもらって、立案後、最終決定を校長先生にお願いすることってありますか?
最終決定権が校長先生にあることは間違いありません。でも細かい業務については、どういった流れで意思決定されているのでしょうか。
みなさんの職員室ではどうなっているでしょうか。
私はそういったことにかなり無頓着だったため、教務主任になるまで、そんなこと考えたこともありませんでした。
でも、ふと疑問に思ったことがきっかけで、理想的な職員室の在り方について、真剣に考えるようになりました。

理想的な意思決定の流れとはどういったものなのか?考えれば考えるほど、奥が深い!
色々と本を読んだり、YouTubeなどで情報収集していると、ホラクラシーという考え方に出会いました。そこからさらにティール組織といった考え方につながっていきました。
簡単に言うと、「意思決定をトップダウンではなく、全員が行う。」という考え方です。学校現場と非常に親和性の高いスタイルだと思います。
先生方が漠然としたイメージで捉えている「意志決定」について、位置づけを明確にし、教職員で共有・実施すれば、より効率的に充実した打ち合わせや会議を持つことができるようになります。
次回は理想的な意思決定の流れについて、より具体的に考えてみたいと思います。

コメント