外から見れば、職員会議で色々と決定しているというイメージですが、今は最終的な意思決定は法律上校長先生が行うことになっています。
でも実際のところ…、「校務」に関わる意思決定の量は恐ろしく膨大です。その全てを校長先生が一つ一ひとつ最終決定することは不可能です。
ではどういったルートで、誰が意思決定しているのでしょうか。
どうも、こんにちは。BigWaveといいます。どこの職員室にもいる「教頭先生」。他の先生たちとは違う、奇妙な生態を持つ教師です。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!
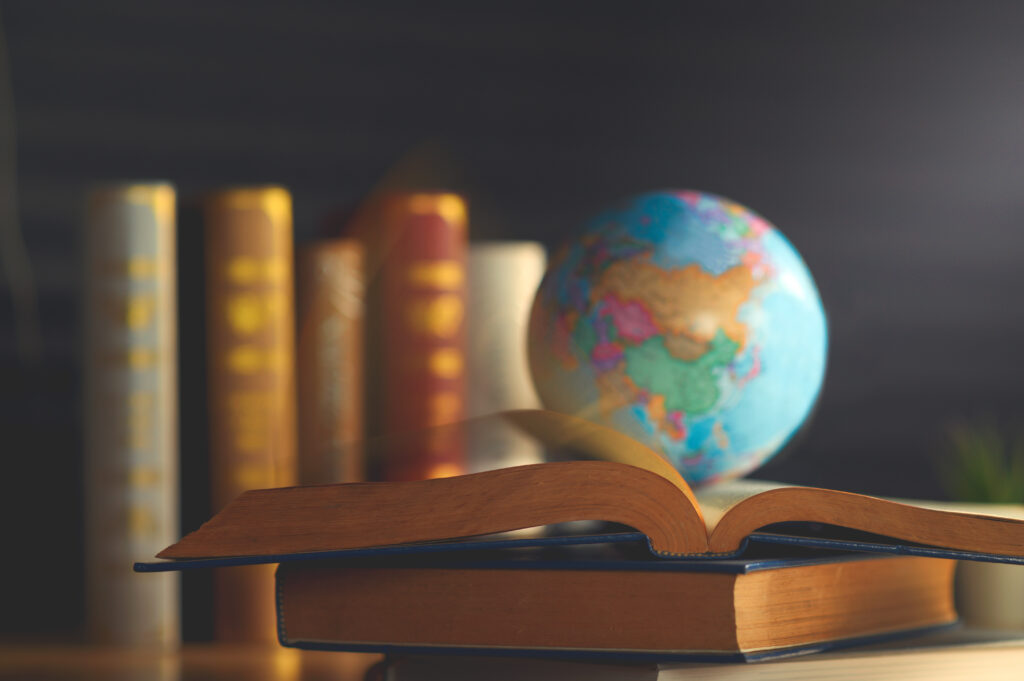
- 3つの決定ルート
- 業務改善の宝庫
職員室という職場には3つの意思決定ルートがあります。
第一のルート(トップダウン)
校長先生を校内のトップとしたトップダウンのルートです。
校内人事や対外的な方針の決定などがあげられます。文科省からの通達や教育委員会からのアンケートの実施なんかもこのルートです。
第二のルート(校長先生による決定)
生徒活動部や学習指導部(研究部?)などの校務分担で立案・検討するルートです。
これは体育大会や卒業式などの行事運営、生徒指導方針などの学校全体に関わる取り組みが対象です。
各部での検討の後、職員会議や前段階で行われる企画会議(運営会議・推進会議とも呼ばれる)において、校長先生により最終決定されます。企画会議・職員会議は校長先生が運営・管理します。
第三のルート(ルートがよく分からない決定)
学年単位での取り組みや生徒委員会活動、クラブ活動などに関わる立案・検討・決定のルートです。
ここでの取り組みでは、校長先生による最終の意思決定はあまり重要視されていません。
もちろん、学校運営方針などが立案のベースになっていると考えられるので、そもそも校長先生の意思が入っていると考えることもできます。

あと、中学校では教科単位での取り組みなんかもあります。これは校務分掌上は学習指導部(研究部)にありますが、決定ルートとしては第三ルートになったりもします。
管理職の先生方にとってみれば、言わずと知れた事かもしれません。でも若手の先生方はもちろん、中堅の先生方でもよく分かっていない方がけっこういるように思います。
「このような意思決定のルートなんて、分かっていなくても毎日の業務は上手く回っているので、特に課題を感じない。」のがほとんどの学校現場だと思います。
今のまま業務を行うのなら、これまで通り分かっていなくてもいいのかもしれません。しかし、今は学校現場にも大きな変化が求められています。
この意思決定のルートに職員室の働き方改革を加速させるヒントがあります。まずは現状の確認と共有が必要不可欠です。意思決定のルートを今の形から少し変化させ、教職員全員が理解し実行することが大切です。
そうすることで、先生方の自己肯定感の向上や生徒への指導力向上、効率的で充実した会議の運営など、OJT推進や人材育成、働き方改革に繋げていくことができます。
学校という職場は、ほんの数年で管理職が入れ替わり、メンバーも5年ほどで8割が異動するので、人材育成を計画的に継続的に行うことが非常に難しいです。
しかし業務改善、働き方改革、人材育成、この3つが同時に見込めるのなら、やってみる価値は十分あると思いませんか?
次回はさらに詳しく考えてみたいと思います。

コメント