最近ニュースでも「教師の働き方改革」ってよく聞きます。でも「5年前から何も変わっていない…。」なんて職員室も多いと思います。
実際のところ、何をすれば改革になるのでしょうか。
どうも、こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。どこの職員室にもいる「教頭先生」。他の先生たちとは違う、奇妙な生態を持つ教師です。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

- 今ある当たり前に疑問を持つ。
- 生徒と一緒に成長する。
毎日「当たり前」に行っている業務ってありますか?5つほど思い出してみてください。
「当たり前」って、言い方を変えれば、「考えなくてもいい」ということです。それはメリットでもありますが、デメリットでもあります。
「当たり前」は「思考停止」を作り出します。
これは「考えられない人」を作ることにもつながります。皆さんはどうですか?私は40歳を過ぎるまで、まさにこの「考えられない人」でした。
考えられないので、認識できません。もちろんそれを変えようとも思いません。

自分が働く中で「当たり前」に行っていることって何でしょうか。思い当たることはありますか?
それは骨身にしみ込んだ考え方やルーティーンなので、見つけることから難しいです。無意識に「変えられない」といったバイアスがかかっている場合もあります。
学校にある「当たり前」なことは、始めはしっかりと考え、議論し、検討し、確認し、決定、実行、継続を経て、今「当たり前」になっています。
打ち上げられるロケットのように、「当たり前」になるまでは、一定期間の継続的で大きな推進力が必要です。
しかし一旦軌道に乗ると、あとはほぼ何もしなくても進み続けます。
そんなことが学校現場では山のようにあります。それは時に、「伝統」という名前を授かったりします。みんなが納得する「当たり前」が継続されるのは、提案も議論の時間も必要ないので、とても効率的だと思います。これまでの先輩方が時間をかけて築いてくれた財産だと思います。
でも一方で???な「当たり前」もあります。そんな「当たり前」何か思いつきませんか?
その???な当たり前をネタに、一度話しやすい人と雑談してみてください。話が盛り上がったら、次は学年主任や教務主任の先生に意見を聞いてみてください。
働き方改革の第一歩は、まずは疑問に思って周りと共有することです。

これで、少なくとも自分の働き方を客観的に見る視点を持つことができます。いろいろな人の意見を聞いて、自分でしっかり考えた結果、納得のいく「当たり前」も出てきます。その場合はさらに自信をもって、その「当たり前」を継続できます。
一方、納得できないことも出てきます。それが「働き方改革」につながります。
生徒に求める「主体的で対話的で深い学び」は、これからの社会を生きるうえで必要な力です。
では、今を生きる私たちにとってはどうなのでしょうか。「これからの社会」はもう始まっています。
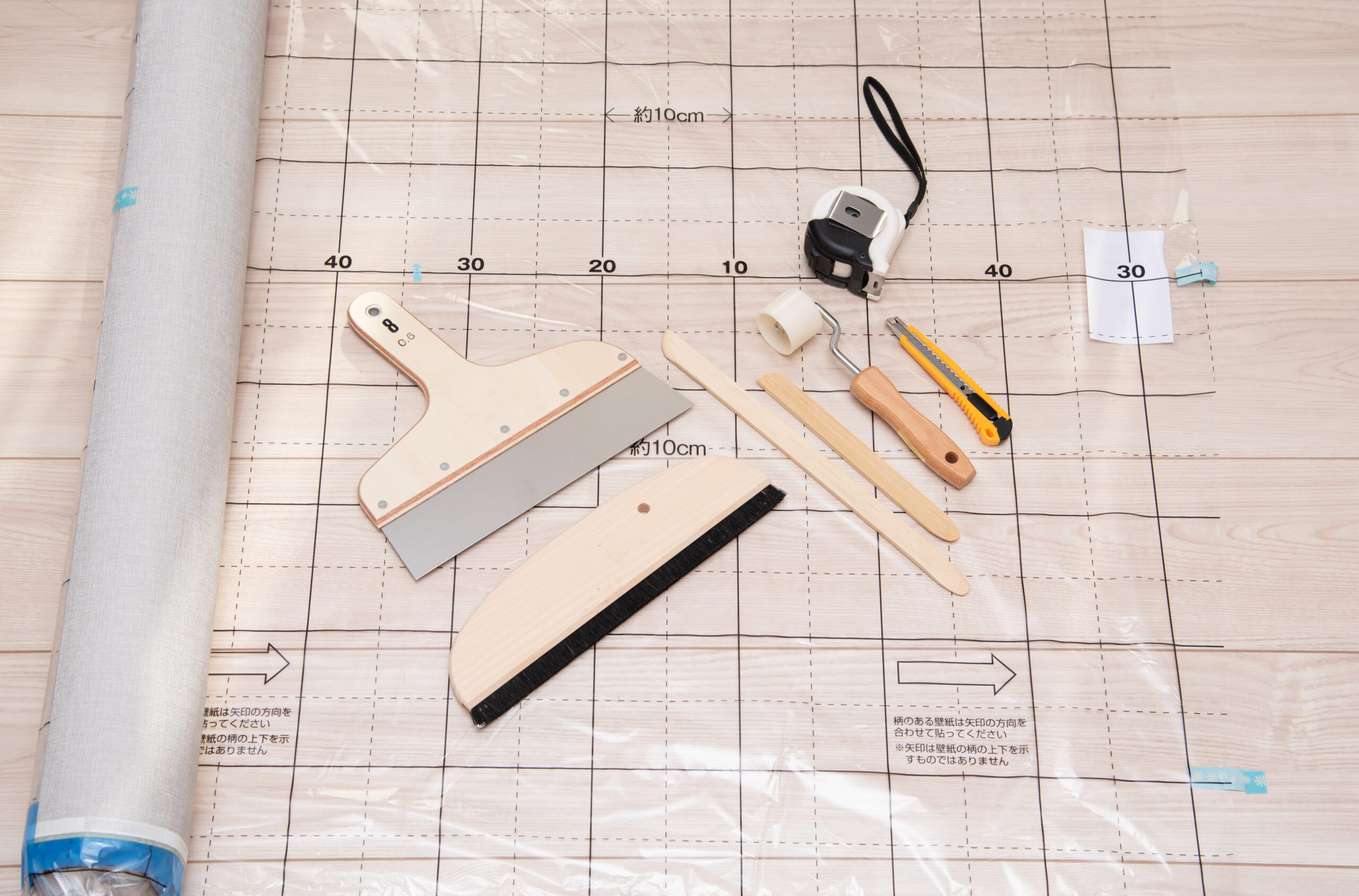
コメント