みなさんの学校では生成AIを校務や授業で使われていますか?
本市では、教職員の活用は可能ですが、生徒の活用にはまだGOサインが出ていません。でも家庭で使っている生徒は急速に増えていると思います。文科省のガイドライン(ver.2)には「AIリテラシー」なる言葉も出てきました。
生成AIは今後広まりこそすれ、消えて無くなることはありません。学校現場ではどのように生成AIと付き合っていけばいいのでしょうか?
こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

→スマホと同じように、手放せない必需品に
最近、生成AIが学校に入ってくるとどうなるんだろうと考えます。試しに文科省が開催しているWeb研修なんかにも顔を出してみます。しかしどうもピンと来ません。
そんな中、隣の中学校から研修で生成AIの話をしてもらいたいというオファーをいただきました。他校で研修なんてしたことが無かったので、どうしようかと思ったのですが、これは自分が勉強するいい機会だと思い、お話を受けることにしました。
研修では
1.生成AIへの期待・不安・疑問
2.生成AIを使ってみる
3.なぜ生成AIが必要なのか?
の3つについて、お話ししました。研修後の感想を見させていただくと、研修の目的だった「不安や疑問を少し解消して、生成AIを使ってみようと思う。」はクリアできたかなと思います。
ここでは「3.なぜ生成AIが必要なのか?」について書いてみようと思います。
1学期にたくさんの作文や絵画の募集要項が届きました。それらの事業の募集要項を見てみると、生成AIについて言及しているものはごく僅かでした。しかも言及していたとしても、「生成AIの使用はできません」といった程度でした。
これにはすごく違和感がありました。
生成AIに全く言及していない募集要項ですが、例年通りに事業を踏襲しているだけなんだと思います。
ネットから拝借して作品を提出してくる生徒が時々現れます。一般常識として盗作はダメですし、事前に指導をしたとしても、時々ネットにあるものを拝借して提出する生徒はいます。
「ダメだと指導したら、全員しない」のは理想論で、人間はそんなに単純ではありません。
学校を窓口として応募するとなると、盗作などの検証は学校側にも一定の責任が発生します。以前、ノミネートの連絡が来た時に、念のため確認したら盗作だったことが判明し、校長先生が謝罪に出向くことがありました。
ネットから丸パクリした場合なら、文面を検索すれば検証できなくもないですが、ものすごい業務量になります。
そして生成AIを使って作成した場合は検索しても意味が無いでしょう。全ては生徒の道徳心・倫理観に委ねられます。教師が一読し、「この生徒がこんな内容を書くかな?」と疑い深く詮索したとして、その結果は生徒との関係悪化しかありません。
生成AIについての言及が全くない事業では、こういったグレーな部分の対応を全て学校に丸投げしているのかと思ってしまいます。
一方、生成AIの使用を禁止している事業にも違和感があります。
盗作については、一般社会の常識として〇か×で言えば、もちろん×になります。おそらく100人いれば100人が×と回答すると思います。
でも生成AIはどうでしょうか?下の内容全て×になるのでしょうか?研修で先生方にも考えてもらいました。
①保護者が代わりに書く
②Web上から拝借する
③自分が書きたい内容を生成AIに伝えて書いてもらう
④生成AIに疑問を投げかけて、アイデア出しをした上で自分の考えをまとめて書く
⑤友人と色々と議論したうえで、自分の考えをまとめて書く
⑥自分一人で考えて書く
研修では、①②③までは満場一致で×でしたが、④はOKだという先生が半数程度いました。⑤はもちろん〇、⑥も〇なのですが、「一人で」の部分が引っかかる先生もいました。
生成AIはWebからの盗作と違って、使用自体が×とは言い切れません。どのように利活用するのか、その方法を使用者に考えさせるのが、これからの生きる力に繋がります。
また現実問題として、生成AIの使用を禁止したとしても、誰も検証することはできません。作文や絵画を公募する中で子どもたちに何を求めているのか、生成AIの登場で改めて考えるいい機会なのではと思います。
学校内でも同じ状況が起こっています。例えば英語。単語を覚えて文法を覚えても、自分が言いたいことが英語で話せないのなら、教科としての英語は受験科目の一つ以上にはなり得ません。
それなら、自分が言いたい内容を、自分が知るべき語彙と文法で、年相応の表現を使って、生成AIに英語に訳してもらうのはどうでしょうか?それなら教科書の本文よりよほど主体的・積極的に覚えようとすると思います。
生成AIが世の中に浸透していくことは間違いありません。スマホが手放せないように、生成AIも手放せなくなる時代がすぐに訪れます。生徒はもちろんみなさん自身も、そんな世の中で生きていくことになります。
教師は生成AIとどう付き合えばいいのでしょうか?次回はもう少し先の未来も見据えて、学校現場はどうなるのかを考えてみたいと思います。
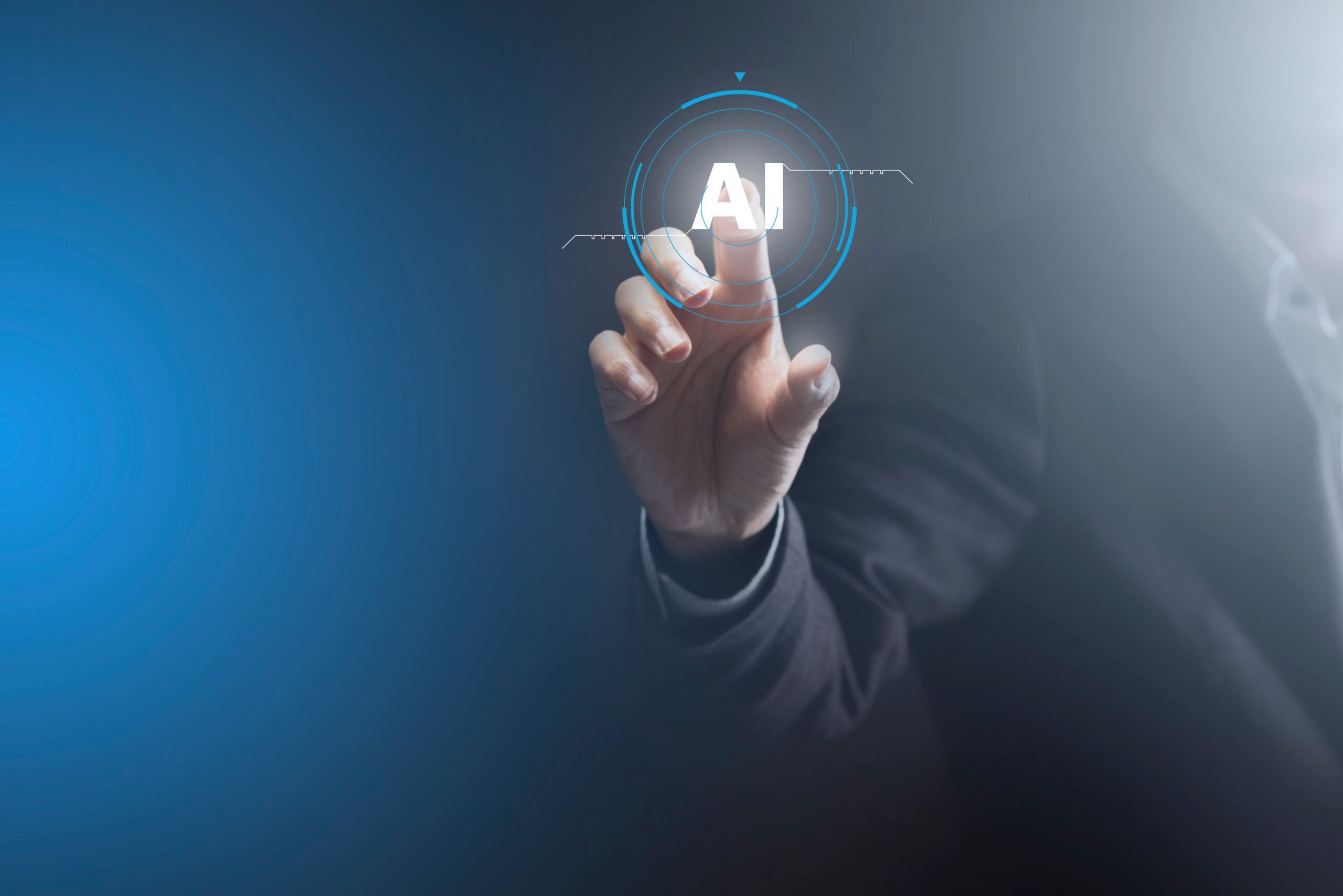
コメント