いよいよ進路指導も大詰めとなってきました。進路選択は3年間の取組みの中でも最大級。
大阪では今年から公立高校もすべてWeb出願となり、その対応も大変です。
進路指導のセオリーに、「進路先は生徒自身に決めさせる。」があります。感覚的にもそう感じるのですが、ではどうして、進路は生徒自身が決めないといけないのでしょうか。
こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!
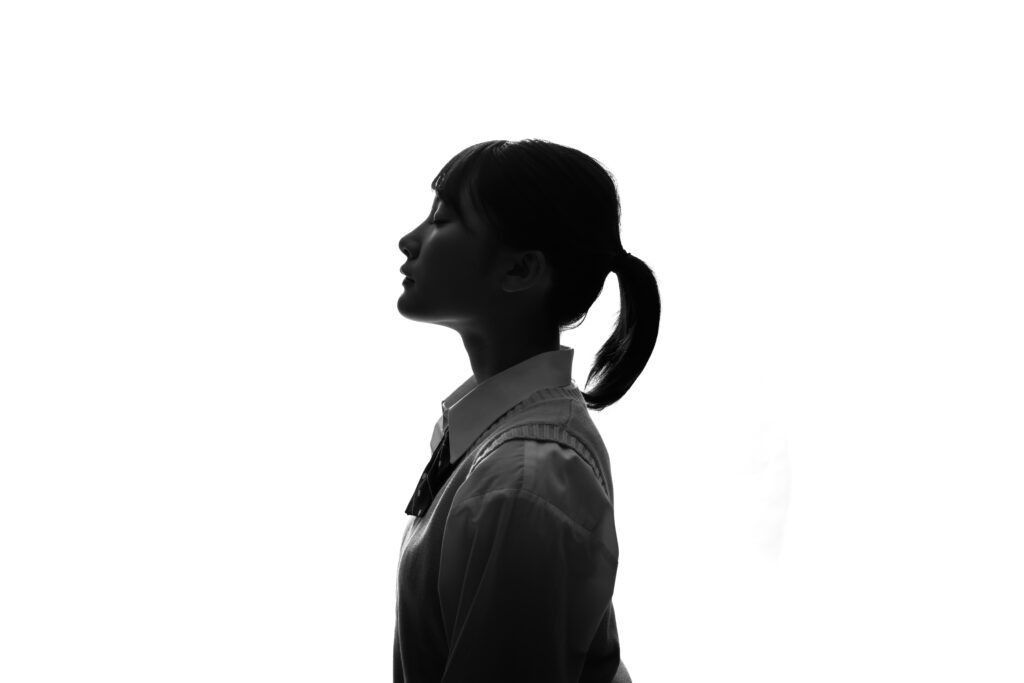
- 自己決定感は内発的動機付けの源
教師になったころ、「進路は生徒自身に決めさせる」と教わりました。3年生を8回経験した今でも、その通りだと考えています。
でも多くの生徒は自分の進路なのに他人事のように無頓着です。(仕方のない事なのですが…)
また保護者が「○○高校以外は許さない!」と断言したり、「塾の指導で…。」といったパターンもよくあることです。
時々、「○○点以上を取ったらお小遣いがもらえる!」と喜んでいる生徒がいます。でもこれは危険信号です。
勉強するのが自分の成長のためではなく、目の前のご褒美のためになってしまっています。
もともと自分が好きで始めたことなのに、ご褒美を与えられたことで以前ほど自発的に取り組まなくなる、という研究結果があります。
目の前の勉強のための外発的な動機付けが、純粋に学びたいという思いを薄れさせていくのです。
これでは徐々に強い外発的動機を得ないと、勉強を継続していくことができなくなってしまいます。もちろん、外発的な動機が無くなると勉強を継続することが難しくなります。
ここで必要なのは、自分自身の中に勉強をする意味を見出せる内発的動機です。
「内発的な動機を高めるためには自己決定感が不可欠であり、自己決定感が低い状態では内発的動機も低下してしまう。」と言われています。
「自分で進路を決める」ことは、この内発的動機を生み出す源になります。「他人からやれと言われた事」と、「自分でやりたいと思った事」ではモチベーションが全く違うということでしょう。
また、自己決定感はレジリエンスにも大きく影響します。
「自己決定感が高ければ、失敗に対しても前向きに捉えることができ、モチベーションが低下しにくい。」とも言われています。この辺りは、教師の経験則から見ても妥当です。
自分で進路を決めることで、「勉強の継続力」と「進学後の粘り強さ」、この2つが向上します。そういった訳で、「進路先は生徒自身に決めさせる。」ことが重要なのです。
ここでもう一つ大事なことがあります。
中学での3年間の最後に行う進路決定は、3年間の集大成となる行事(?)です。
精神的な負荷はこれまでの人生で最大と言えます。
それに立ち向かえるだけの内発的動機付けは、一朝一夕では身につきません。進路決定に向かうまでに時間をかけて養っておく必要があります。
ゲームの最初の敵がラスボスだったら、誰でも逃げ出したくなります。

日頃から自己決定することが重要です。中学校に入学してからじっくり時間を掛けて、自己決定と内発的動機付けの経験を培っておく必要があります。探求学習はまさに理想的な場となります。
付け加えると、これは生徒に限らず大人も一緒です。みなさん自身も自分で自分の行動を決定していますか?やらされている仕事だけでは、気持ちが滅入ってきます。
大人にとっても大事なのは、自己決定感と内発的動機付けです。
日常の色々な場面で、やりたい仕事に力を注いでください。 神戸大の研究によると、自己決定は幸福感にもつながるそうですよ。
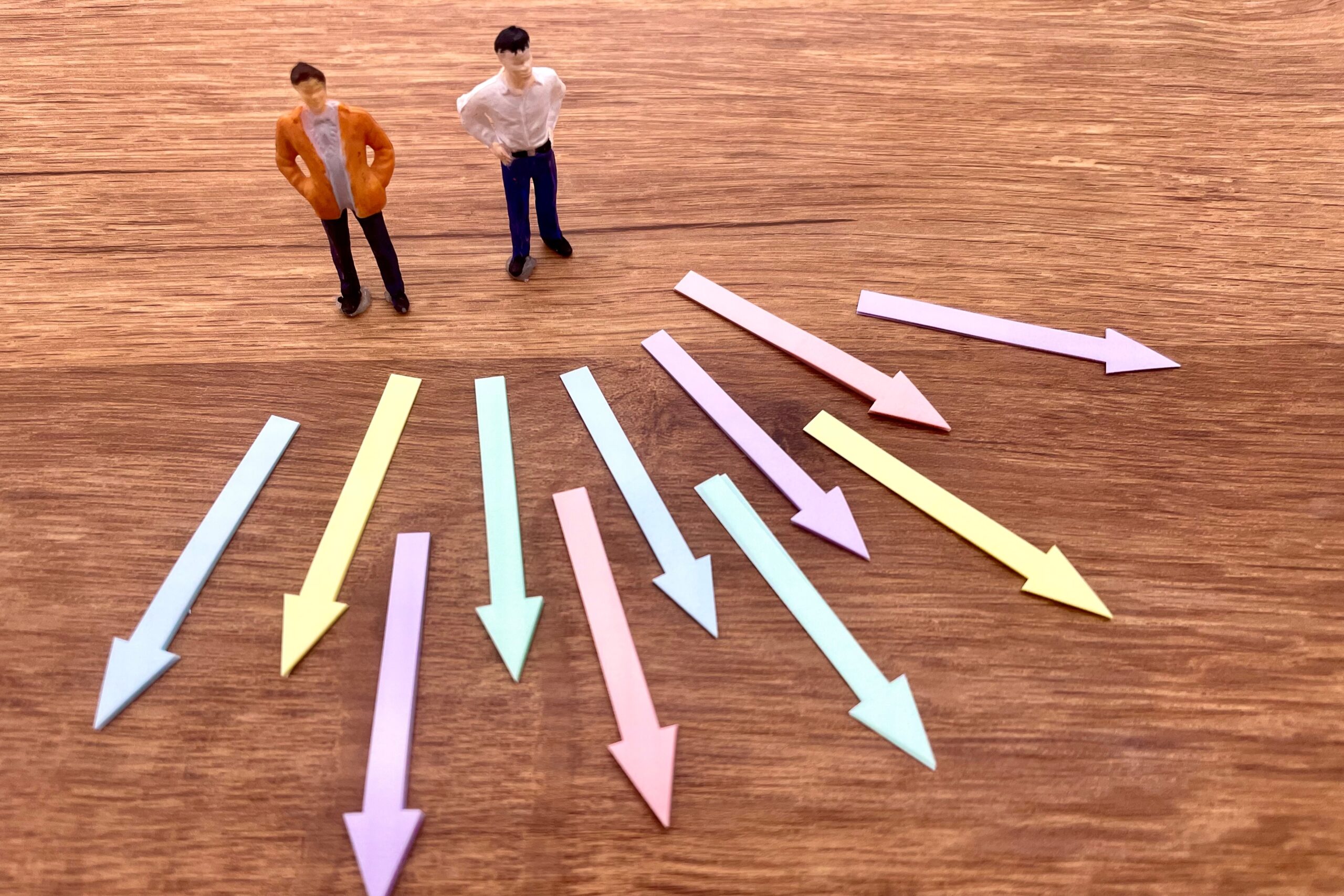
コメント