昨日(2024年2月20日)、大阪府公立小中学校教頭会研究大会に行ってきました。200人以上の教頭先生が集まっていました。
日頃は校内に1人しかいない教頭ですが、昨日は前後左右どこを見ても教頭先生でした。
しかし校務等で参加できなかった教頭先生も大勢いたと思います。面白い話もたくさんあったので、ここで紹介しておきます。
こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

- 外に出ないと分からない。
研究大会には200名を超える教頭先生が集まっていました。近畿の大会になると1000名以上の教頭先生が集まります。
この会場で「教頭先生、お電話です!」と叫んだら、全員振り向くのかなと思うと、ちょっと面白くなってきました。
さて、今回の研修は四天王寺大学の和田先生とGoldratt Japanさんによる2時間の研修でした。
テーマは「学校の課題解決に向けて ~企業経営の手法でともに考える~」。教頭心がくすぶられる内容でした。
こういった研修や学校公開に行くと、普段の自分の状況を客観的に見ることができます。
新しい学びに加え、リフレッシュにもなるので、こういった校外の学びに参加するのがめっちゃ好きです。
今回はTOCという手法を用いた、ボトムアップ型の内容で、これがうわさに聞く企業コンサルティングなのかなと思いながら聞いていました。
まずは事前に行ったアンケートの分析、それからTOC研修の流れの説明、マルチタスクに関する受講者参加型の実験、TOCを活用した事例紹介と続きました。
最後に、教頭の仕事における「望ましい姿」から「今の困りごと」→「現在の障壁」→「横断的な解決」へとつながっていきました。
特に面白かったのが、参加されていた教頭先生方から「困りごと」や「障壁」、「解決案」を募って共有したことです。
「教頭の役割が多い」「欠員による負担増」「分担の再編成は難しい」「重複した調査」等、いろいろな困りごとがありました。
解決案はなかなか出てこなかったのですが、「ICTの活用」「首席(主幹教諭)との分担」などがありました。
その中で、「権限移譲によるチーム会議」と発言された先生がいました。まさに私も考えていることなので、激しく共感し、同じようなチャレンジをされている教頭先生がいることに感激しました。
校外に出て学ぶには業務やスケジュールの調整が必要です。ちょっと面倒ですが、それをするだけの価値は十分あります。
事務処理を延々としたり、市教委からの依頼を淡々とこなしたり、修理箇所を黙々と直していると、発想の柔軟性がなくなってきます。これまで培ってきた経験だけで物事を判断しがちになります。視野が狭くなり、謙虚な姿勢もなくなってきます。
これは本当に怖いことです。柔軟性がなく新しいことを学ぼうとしない管理職に、「授業改善してください。」と言われたら、先生方はどう感じるでしょうか?
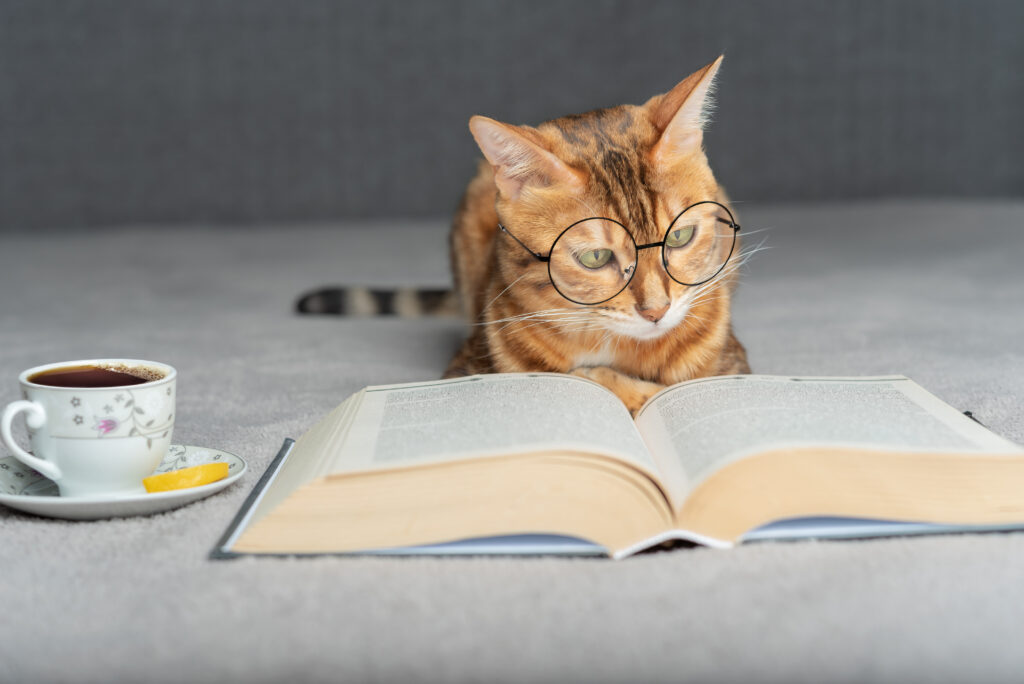
またいつも職員室で「外に出て学ぶことは大事。」と先生方に言っているので、そういう意味でも外で学ぶ機会があれば、有言実行したいです。最近はWeb研修も多いので参加しやすいです。
もちろん、理解のある校長先生の存在はとても重要です。
もし「校外の研修に参加したい」と校長先生に相談しにくいなら、まずはその課題クリアに挑戦するのはどうでしょうか。

コメント